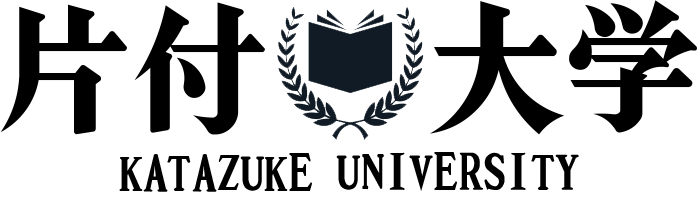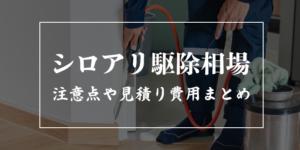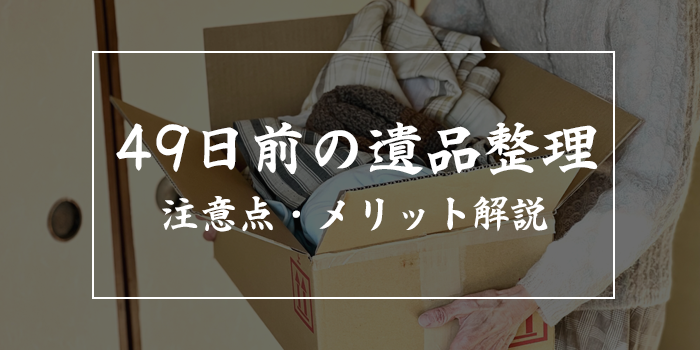

生徒
人が亡くなったら49日間は現世をさまようって言いますよね…
その間に遺品整理をしてしまっても良いのでしょうか?
その間に遺品整理をしてしまっても良いのでしょうか?
もし家族が亡くなってしまったら遺品整理を49日前にしても良いのか、悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺品整理を49日前にするメリットや遺品整理の注意点などについて詳しく解説していきます。

片付先生
49日前に遺品整理をする際には、気をつけることがいくつかあるぞ。
ポイントを抑えて、スムーズに遺品整理ができるようにしっかりと学んでおくのじゃ。
ポイントを抑えて、スムーズに遺品整理ができるようにしっかりと学んでおくのじゃ。
この記事で分かること
-
- 49日前に遺品整理をしても良いのか
- 遺品整理を早く行うメリット
- 49日前に遺品整理を行う注意点やコツ
- 49日前にしてはいけないこと
目次
49日前に遺品整理をしても良い?

遺品整理は、49日前に行っても良いとされています。49日の間に遺品整理をしても、故人の死を悼んでいないということにはならないので、遺品整理を行うことに問題はありません。
仏教においては、故人は49日目に極楽浄土に行けるかが決まると考えられています。遺族は故人が極楽浄土に行くまで、死の穢れを広めないためにおめでたい席を避けるべきだとされていますが、遺品整理はお祝いではないので行っても問題ありません。
遺品整理を早めにやるメリット

遺品整理を早めにやるメリットには、以下の6つがあります。
fa-check遺品整理を早めにやるメリット
- 出費が減る
- 心の整理がつく
- 忌引休暇で遺品整理できる
- 四十九日法要により遺品を形見分けできる
- 部屋を明け渡せる
- 遺族間のトラブルを防げる
それぞれについて詳しく見てみましょう。
出費が減る
遺品整理を早めにやるメリットの1つ目は、出費が減ることです。遺品整理を早く行えば、故人が契約していたサービスなどを早く解約できるので、死後も引き続き発生している利用料などを払う期間が短くて済みます。
スマートフォンやネットサービスの普及で、故人が定期的に利用料を支払っているものも増えてきています。

片付先生
遺品整理を行えば、どのサービスに加入しているのかがわかり、早く解約できるぞ。
心の整理がつく
遺品整理を早めにやるメリットには、心の整理がつくことがあります。遺品を整理しているうちに、大切な人が亡くなった現実を受け止められるようになるでしょう。
人が亡くなると、相続や各種手続きなど、しなければならないことがたくさんある上に、期限が決まっているものがほとんどです。遺品整理を早く行えば、期限を気にすることもなくなり、不安が軽減されることでゆっくり故人と向き合えるようになります。
忌引休暇で遺品整理できる
遺品整理を早めにやるメリットには、忌引休暇で遺品整理ができることがあります。仕事に行く必要がないので遺品整理に集中でき、効率よく進められるでしょう。
遺品整理の手続きには、役所に行かないといけないものもあります。普段平日に仕事をしていても、忌引休暇中であれば手続きも含めた遺品整理が可能となり、短期間でスムーズに遺品整理ができます。
四十九日法要により遺品を形見分けできる
遺品整理を早めにやるメリットには、四十九日法要により遺品を形見分けできることも挙げられます。遺品整理を早めに行えば、誰に何を渡すのか決めたり持ち帰る準備をしたりできます。
四十九日法要は、遺品の形見分けをする故人の親族や親しかった人たちが集まる場です。この日までに遺品整理が終わっていない場合は、なかなか形見分けをする人たちが一度に集まる機会もなく、個別に渡しに行く必要があります。

片付先生
49日前に遺品整理をすれば、効率よく形見分けができるんじゃ。
部屋を明け渡せる
遺品整理を早めにやるメリットとして、故人の部屋を明け渡すことが可能です。故人が賃貸住宅に住んでいた場合、部屋を整理して中に物がない状態にしないと解約ができません。
アパートやマンションなどの賃貸住宅は、たとえ人が亡くなったとしても明け渡すまで賃料がかかります。賃料の支払いは相続人が行う必要があるので、早く遺品整理をして部屋を明け渡しましょう。
遺族間のトラブルを防げる
遺品整理を早めにやるメリットには、遺族間のトラブルを防げることもあります。遺品整理を行う際には遺族間で意見が割れる可能性がありますが、早めに遺品整理を行えば話し合いの機会を設けることができるので、トラブルになりづらいです。
遺品整理では、誰が何を相続するかや、遺品整理を業者に頼んだ場合にその費用を誰が負担するかについて、遺族同士で意見が異なる場合があります。四十九日法要までは遺族が集まる機会が増えるので、意見が違っても十分に話し合う時間を取ることができ、双方が納得した回答が得られる可能性が高まるでしょう。
49日前に遺品整理を行う際の注意点

遺品整理を49日前に行う際には、以下の点に注意しましょう。
fa-check49日前に遺品整理を行う際の注意点
- 他の遺族の同意を得てから行う
- 相続放棄ができなくなるケースがある
- 重要書類や大切なものまで捨てないよう注意する
- 近所迷惑にならないようにする
- 大きな荷物は1人で運ばない
それぞれについて詳しく解説していきます。
他の遺族の同意を得てから行う
49日前に遺品整理を行う際の注意点には、他の遺族の同意を得てから行いましょう。同意を得ずに勝手に遺品整理を行うと、トラブルに発展する可能性もあります。
遺品整理は人によって行うタイミングが異なるため、49日後に行うと思っている親族もいるかもしれません。少なくとも、法律上相続の権利がある人には伝えておきましょう。
民法では、故人の配偶者、親と子、兄弟姉妹が相続人になれると定められているので、遺品整理について共有する必要があります。

片付先生
後々のトラブルを防ぐためにも、事前に同意を得ておこう。
相続放棄ができなくなるケースがある
49日前に遺品整理を行う際の注意点として、相続放棄ができなくなるケースがあるので、注意が必要です。遺品整理を行って、遺品を処分したり預金を引き出したりすると、相続を認めたとみなされて相続放棄ができなくなります。
相続は、財産だけでなく借金や負債も対象となるため、故人に借金や負債があると相続放棄を行うことが多いです。相続放棄するには、必要書類を家庭裁判所に提出して受理書をもらう必要があります。相続放棄の可能性がある場合は手続き中に遺品整理をしないようにしましょう。
重要書類や大切なものまで捨てないよう注意する
49日前に遺品整理を行う際の注意点には、重要書類や大切なものまで捨てないよう注意することも挙げられます。重要なものを捨ててしまうと、相続や契約の手続きができなくなってしまうのです。
公的手続きや相続、各種契約解除などで必要となるものには、以下が挙げられます。
- 遺言書
- 身分証明書
- 仕事関係の書類
- 請求書・支払通知書
- 年金手帳
- 印鑑
- デジタル遺品
特に、スマートフォンやパソコンなどの端末やその内部データなどのデジタル遺品は、見落とされがちです。オンライン上での契約の解除などで必要となることがあるので、大切に保管しましょう。
近所迷惑にならないようにする
遺品整理を49日前に行う際には、近所迷惑にならないようにしましょう。遺品整理の際には、大きな荷物を運び出したり大きな音を立ててしまう可能性があるので、近所の人とトラブルにならないように配慮が必要です。
近所迷惑にならないようにするためには、大きな音を外に漏らさないように工夫をしましょう。ドアや窓を開けたままの作業を控え、大声で会話を控えることで、騒音を軽減することができます。マンションやアパートでは、荷物を持ってマンション内を移動することになるので、事前に挨拶をしておくことも効果的です。

片付先生
マンションやアパートでは、事前に挨拶をしておくことも効果的じゃぞ。
大きな荷物は1人で運ばない
遺品整理を49日前に行う場合は、大きな荷物を1人で運ばないようにしましょう。大切な人が亡くなり、気持ちが落ち着いていない時に大きな荷物を1人で運ぶと、普段よりも注意力が散漫になり事故につながる可能性もあります。
特に、冷蔵庫などの大型家電や家具類は、大人2人以上で注意しながら運ぶようにしましょう。難しい場合は、遺品整理業者に頼むこともおすすめです。
49日前に遺品整理を行う方法

49日前に遺品整理を行う際は、以下の方法で行いましょう。
fa-check49日前に遺品整理を行う方法
- 葬儀が終わってから取り掛かる
- 現場の様子を確認する
- 遺品整理をする時期を決める
- 捨てるもの・残すものに分類する
- リサイクル品を仕分けする
- 不用品を処分する
- 清掃を行う
それぞれについて詳細を解説します。
葬儀が終わってから取り掛かる
49日前に遺品整理を行う方法には、葬儀が終わってから取り掛かることがあります。葬儀の前に遺品整理をしてしまうと、他の遺族や親戚から故人を偲ぶ気持ちがないと非難されることがあります。
特にご年配の方や宗教を大切にしている方は、遺品整理を早く行うという考えを持っていない場合もあります。葬儀前で気持ちが落ち着いていない時に遺品整理をすると、大事なものを誤って捨ててしまったり、思わぬ事故につながったりする可能性もあるので、注意しましょう。

片付先生
葬儀後の気持ちが落ち着いたころから始めると良いだろう。
現場の様子を確認する
49日前に遺品整理を行う方法は、まず現場の様子を確認しましょう。遺品の種類や状況を確認しておくことで、遺品整理に必要な人手や期間を予想することができます。
散らかっていないように見えても、押し入れを開くと大量のものがある場合が多いです。現場の様子を確認する際は、収納の中も確認してどれくらいの物があるのかを把握しておきましょう。
遺品整理をする時期を決める
49日前に遺品整理を行う方法として、遺品整理をする時期を決めておくことも重要なポイントです。遺品整理の時期を決めて計画的に行い、重要な書類などの所在を把握しておくことで、公的手続きなどを期限内に行えます。
遺品整理をする時期を決める際は、親族と相談して決めましょう。遺品整理は1日~1週間、遺品が多いと1か月以上かかることもあり、1人で行うことは困難です。親族の手助けが必要となるので、事前に相談して時期を決めるようにしましょう。
捨てるもの・残すものに分類する
49日前に遺品整理を行う方法には、捨てるものと残すものに分類することが有効です。先に分類しておけば、スムーズに遺品整理を行うことができます。
捨てるものと残すものを分類する時には、以下の3つのポイントを参考にしましょう。
- 捨ててはいけない物かどうか
- 相続する可能性があるかどうか
- 故人の思い出が詰まった物かどうか
一度捨ててしまうと元には戻らないので、遺族で話し合いながら慎重に分類する必要があります。

片付先生
大切なものは親族と話し合って分類方法を決めるんじゃ。
リサイクル品を仕分けする
49日前に遺品整理を行う方法として、リサイクル品を仕分けすることもおすすめです。リサイクル品を買取に出すことで、遺品整理の費用を抑えることができます。
リサイクル品には、以下の物があります。
- 古紙類(段ボール、新聞など)
- 鉄くず類
- プラスチック類(ペットボトル、発泡スチロールなど)
- 衣類
- 漫画、雑誌
- 家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)
- 家具
- 自転車
買取業者によって買い取ってもらえるものが異なる場合があるので、仕分けたあとに業者に連絡して確認しましょう。
不用品を処分する
49日前に遺品整理を行う方法として、不用品があった場合は処分しましょう。特に賃貸住宅の場合は、明け渡す必要があるので、不用品は早めに処分する必要があります。
不用品は、自治体でごみとして処分することができます。可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみなど、自治体の分別方法に従いましょう。自治体で回収できないテレビやエアコン、石などは、不用品回収業者に連絡すれば処分してもらえます。
清掃を行う
49日前に遺品整理を行う方法には、清掃を行うこともあります。次に住む人や物件を賃貸に出す際に、より良い印象を与えることができるので、部屋全体を清掃することがおすすめです。
遺品整理後の部屋には、長年の生活で生じた汚れが蓄積されています。全体的な掃除が必要となるので、自分で行うのが難しい場合は業者に頼むことも検討しましょう。

片付先生
部屋の大きさにもよるが、数万円で清掃してもらえるぞ。
遺品整理をスムーズに進めるコツ

遺品整理をスムーズに進めるコツには、以下の3つが挙げられます。
fa-check遺品整理をスムーズに進めるコツ
- 複数人で作業する
- 必要に応じて業者に依頼する
- 重要な書類や貴重品は先に探す
それぞれについて詳細を確認していきましょう。
複数人で作業する
遺品整理をスムーズに進めるコツは、複数人で作業することです。故人が生前に整理していない場合、大量の遺品を整理する必要があり、1人では時間がかかってしまいます。
基本的には、親族が複数人で作業するのが理想です。相続の相談をしながら作業できるので、効率的に遺品整理を進めることができます。親族以外の人が手伝いに入ると後々トラブルになる場合もあるので、やむを得ない場合にのみ、事前に他の遺族の了承を得てから手伝ってもらいましょう。
必要に応じて業者に依頼する
遺品整理をスムーズに進めるコツとして、必要に応じて業者に依頼することも検討しましょう。業者に依頼すれば、遺品整理に関する面倒な作業を代わりにしてもらうことができ、負担が減ります。
業者によっては、遺品整理士という遺品整理のプロが、法的な知識に基づいてどの遺品が遺産として相続の対象になるか選別してくれます。相場は、部屋の間取りや荷物量などによって異なりますが、10万円前後の場合が多いです。
重要な書類や貴重品は先に探す
遺品整理をスムーズに進めるコツには、必要な書類や貴重品を先に探すこともあります。重要な書類や貴重品を先に探しておけば、誤って捨ててしまうリスクを減らせます。
先に探すべき書類や貴重品には、以下が挙げられます。
- 遺言書
- 身分証明書
- 各種契約書
- 年金関係の書類
- 現金・通帳
- 銀行印・実印
- 結婚指輪
- 貴金属
- 骨董品・美術品
- 鍵
- 携帯電話
見つけた後は、ひとまとめにしてなくさないように保管しておきましょう。

片付先生
遺品整理をする前にリストアップしておくと、スムーズに探すことができるんじゃ。
49日前にしてはいけないことはある?

49日前にしてはいけないことには、以下の3つがあります。
fa-check49日前にしてはいけないこと
- お祝い事への参加
- お中元やお歳暮
- 引越しや家の新築
それぞれについて、なぜしてはいけないのか詳しく解説します。
お祝い事への参加
49日前は、お祝い事への参加は控えましょう。49日前は死の穢れを広めてしまうと考えられています。
四十九日法要が済めば、お祝い事へ参加しても構いません。ただし、喪中は1年間続くので、喪中の場合は事前に主催者にその旨を伝えて相談するのがマナーです。
お中元やお歳暮
49日前にお中元やお歳暮は送らない方が良いでしょう。絶対に送ってはいけない訳ではありませんが、お中元やお歳暮を送ると、送った相手に死の穢れを広めてしまうと考えられており、送らない方が無難です。
もしどうしても送る必要がある場合は、のし紙に注意しましょう。一般的にのし紙には、紅白の水引が使われますが、49日の間に送る際は白色無地の奉書紙か白色の短冊を使います。
引越しや家の新築
49日前に引越しや家の新築の予定がある場合は、可能な限り延期しましょう。49日の間は故人がまだ現世にいると考えられているので、故人が過ごした家で最後のお別れをするためにも、引越しや家の新築は避けた方が良いと言われています。
ただし、自身の生活を優先せずに故人のことばかり思って生活に支障が出るのは故人も悲しむ、という考えに基づいて、引越しや家の新築をしても良いという意見もあります。会社や学校など、手続き上延期するのが難しい場合は検討しましょう。

片付先生
やむなく引越しや家の新築を行った時は、住所が変わったことを喪中はがきで簡単に伝えるのがおすすめじゃ。
葬儀・告別式の翌日や初七日前から遺品整理をしてもいい?

遺品整理は、葬儀・告別式の翌日や初七日から行っても良いです。
その理由として、以下の3つがあります。
fa-check葬儀・告別式の翌日や初七日前から遺品整理をしても良い理由
- 仏教の教義として問題はない
- 初七日や四十九日の存在理由ともぶつからない
- 他の家族・親戚・親族の感情にも配慮した上で行う
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
仏教の教義として問題はない
遺品整理を葬儀・告別式の翌日や初七日前から行うことは、仏教の教義としても問題はありません。仏教の一般的な宗派では、亡くなってすぐに遺品整理をすることについて、特に制限は設けられていません。
ただし、特殊な宗派では制限がある可能性もあります。故人が宗教的であった場合は、確認してから遺品整理を行うようにしましょう。
初七日や四十九日の存在理由ともぶつからない
遺品整理を葬儀・告別式の翌日や初七日前から行うことは、初七日や四十九日の存在理由ともぶつからないです。初七日や四十九日は閻魔様の裁きを受けるタイミングであるから法要を行う、というものなので、遺品整理とは関係ありません。
仏教では、人は亡くなると現世と来世の間を49日間さまよい、その間は7日ごとに閻魔様の裁きを受けると考えられています。初七日は、故人が三途の川に到着する日であり、四十九日は最後の審判が行われる日であるため法要が行われます。遺品整理は遺族が行うもので、法要とは違い宗教的意味を持たないので、安心して行いましょう。
他の家族・親戚・親族の感情にも配慮した上で行う
遺品整理を葬儀・告別式の翌日や初七日前から行う際は、他の家族・親戚・親族の感情にも配慮した上で行いましょう。宗教的には問題がなくても、遺族の中には心の整理がついていない人もいるかもしれないので、十分な配慮が必要です。
いきなり遺品整理をはじめるのではなく、他の遺族にも事前に伝えるようにしましょう。

片付先生
もし「遺品整理はまだ早い」という親族がいる場合、意見を尊重して無理に進めないようにするんじゃ。
遺品整理は四十九日の後でも問題なし!ただし先に延ばすときは注意

遺品整理は四十九日の後でも問題ありません。しかし、先延ばしにしすぎることで以下のような問題が生じるおそれがあるので、注意しましょう。
fa-check遺品整理を先延ばしにすると起こる可能性のある問題
- 空き家になる場合は火災・侵入・不法投棄のリスクがある
- 相続税の申告期限を過ぎてしまう
それぞれについて詳しく見てみましょう。
空き家になる場合は火災・侵入・不法投棄のリスクがある
遺品整理を先延ばしにすると、空き家になった場合の火災・侵入・不法投棄のリスクが問題となります。空き家の手入れを怠ることで、草木が生えっぱなしになり人気が無くなるので、様々なリスクが生じます。
空き家は、手入れを怠った際にガス漏れや配線機器の不具合で火災になることも少なくありません。遺品整理を先延ばしにして物が多い状態になっていると、燃える物が多いことで火の勢いが増し、近隣の家屋に延焼する可能性も高まります。また、空き家は人気が無いため犯罪者のターゲットになりやすく、侵入や不法投棄のリスクが高まるでしょう。

片付先生
近所の人に迷惑をかけないためにも、遺品整理は早めに行うんじゃぞ。
相続税の申告期限は死後10カ月以内
遺品整理を先延ばしにすると、知らない間に相続税の申告期限を過ぎてしまう場合があります。相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に申告しないといけないと、法律で定められています。
申告期限をすぎてしまうと、税金が加算されたり延滞税の支払いが必要になったりする場合があります。ただし、相続税は相続する財産の総額が、3,000万円+600万円×法定相続人の人数で計算される金額以下の場合かかりません。相続税の有無を調べて期間内に申告するために、遺品整理は早めに行いましょう。