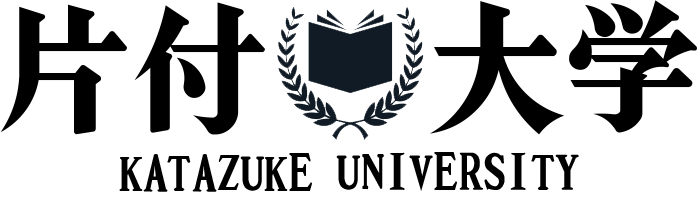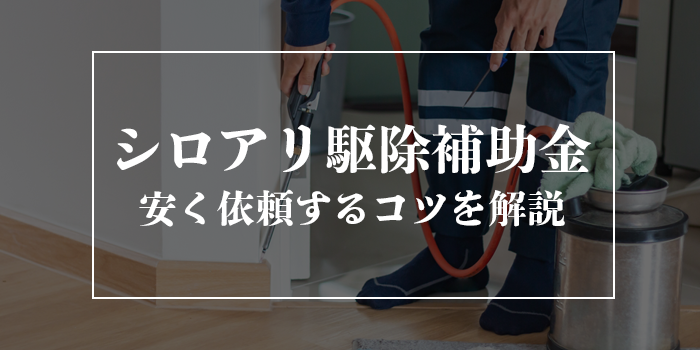

極力お得に実施する方法を知りたい・・・
シロアリ駆除を考えていても、補助金などの制度を知らず、費用が心配で躊躇してしまう方は多いでしょう。
この記事ではシロアリ駆除に関する補助金や費用相場、安く実施するコツ等について詳しく解説していきます。

- シロアリ駆除の費用相場
- シロアリ駆除を安くするコツ
- シロアリ駆除で活用できる雑損控除
- シロアリ駆除におすすめの業者
目次
- 1 シロアリ駆除を対象とした補助金制度はない
- 2 補助金が使えないと高い?シロアリ駆除の費用相場と内訳
- 3 補助金対象外のシロアリ駆除費用を安くするコツ
- 4 シロアリ駆除に補助金はないが火災保険が適用されるケースはある
- 5 シロアリの駆除費用を抑えるなら雑損控除を活用しよう
- 6 シロアリ駆除で雑損控除を利用する際の注意点
- 7 補助金は出ないがシロアリ駆除が負担されるケース
- 8 補助金が出ない場合にチェック!シロアリの駆除費用自体を安くする方法
- 9 シロアリ駆除の資金が用意できない場合はどうする?
- 10 シロアリ駆除に補助金は出ないが費用の安さを売りにする業者には注意
- 11 補助金対象外のシロアリ駆除におすすめな業者4選
シロアリ駆除を対象とした補助金制度はない

現在、シロアリ駆除を対象とした補助金制度は残念ながらありません。その理由などについて以下の項目に分けて解説します。
- 自治体から補助金は出ない
- 火災保険が適用される可能性も少ない
詳しく見ていきましょう。
自治体からシロアリ駆除の補助金は出ない
シロアリ駆除に対して、自治体から補助金が出ることはほとんどありません。一部の地域ではシロアリなどの害虫駆除に補助金を出しているケースもありますが、多くの自治体では補助金を支給していないのが現状です。
自分の住む地域でシロアリ駆除の補助金があるかどうか気になる方は、市区町村の役所窓口で確認してみると良いでしょう。
シロアリ駆除は火災保険が適用される可能性も少ない
シロアリ駆除は、火災保険が適用される可能性も期待できません。一般的に、個人向けの火災保険は突発的な事故や自然災害で自宅に被害があった場合に適用されます。
シロアリは時間をかけて状態が進行していくため、火災保険の対象外となります。しかし、以下のケースでは支払い対象となる可能性もあるでしょう。
- 台風の被害で屋根が損傷し、雨漏りが原因でシロアリが発生した
- 大雪により屋根が破損し、内部が湿ったことでシロアリが発生した
自然災害が原因でシロアリ被害が発生したことを証明する必要があるため、気になる方は保険会社に相談してみてください。
補助金が使えないと高い?シロアリ駆除の費用相場と内訳

シロアリ駆除の費用相場は、10~15万円ほどです。内訳には以下のものがあります。
- 駆除作業にかかる費用
- 薬剤にかかる費用
- 防腐対策にかかる費用
一つずつ解説します。
シロアリ駆除費用内訳①駆除作業にかかる費用
シロアリの駆除作業にかかる費用には、以下の項目が含まれています。
- 駆除の作業費用
- 人件費
- 清掃や養生費
コンクリートを削る場合には、さらにハツリ工事費が加算されます。


シロアリ駆除費用内訳Ⅱ薬剤にかかる費用
シロアリ駆除には、薬剤の費用もかかります。薬剤は施工範囲が広いほど使用量も多くなり、費用も高額になる傾向です。
シロアリ駆除費用内訳③防腐対策にかかる費用
シロアリ駆除の防腐対策にかかる費用も忘れてはいけません。シロアリを駆除しただけでは再発の恐れがあるため、木材の防腐対策も行われます。
必須の作業ではないため、被害状況などに応じて判断しましょう。
補助金対象外のシロアリ駆除費用を安くするコツ

補助金対象外のシロアリ駆除費用を安くするコツは以下の3つです。
- なるべく早く駆除する
- 自分でシロアリを駆除する
- 複数の業者で相見積もりを取る
詳しく見ていきましょう。
なるべく早く駆除する
補助金対象外のシロアリ駆除費用を安くするコツは、なるべく早く駆除することです。被害が大きくなるほど駆除費用も高くなるため、被害が小さいうちに対処する必要があります。
シロアリが発生する前の処置として、予防対策をしておくのも効果的です。予防対策の薬剤の有効期間は約1~5年ほどのため、定期的に依頼すると良いでしょう。

自分でシロアリを駆除する
補助金対象外のシロアリ駆除費用を安くするコツとして、自分でシロアリを駆除することが挙げられます。
たとえば、30坪の施工を自分で駆除した場合と、業者に依頼した場合の費用相場は以下のようになります。
- 自力:約41,000円
- 業者:約322,000円
費用面では大幅に節約できますが、自力では手間がかかり再発のリスクも高いです。よく検討したうえで自力で行うのか、業者に依頼するのかを決断してください。
複数の業者で相見積もりを取る
補助金対象外のシロアリ駆除費用を安くするコツの3つ目は、複数の業者で相見積もりを取ることです。
シロアリ駆除は、業者によってかかる費用が異なります。少なくとも2~3社に見積もりを依頼すると、適正な相場や作業内容を把握できます。
そのなかから、対応や作業内容、費用に納得できる業者を選びましょう。
シロアリ駆除に補助金はないが火災保険が適用されるケースはある

シロアリ駆除に補助金はでませんが、火災保険が適用されるケースはあります。そのケースを、以下の項目に分けて解説します。
- ケース①台風による雨漏りが原因でシロアリが発生した
- ケース②自然災害が原因でシロアリが発生した
- ケース③雪が原因でシロアリが発生した
- シロアリ駆除で火災保険が適用される際の注意点
詳しく見ていきましょう。
ケース①台風による雨漏りが原因でシロアリが発生した
シロアリ駆除に火災保険が適用されるケースとして、台風による雨漏りが原因でシロアリが発生した場合が挙げられます。
火災保険は自然災害による被害に適用されるため、台風が原因でシロアリが発生した場合火災保険も適用されやすくなります。
たとえば、台風の強い風で屋根がめくれ、雨漏りが発生し、周囲の木材が湿ったことでシロアリが発生したケースです。
自然災害である台風とシロアリ被害がつながっているため、火災保険で補償される可能性があります。


ケース②自然災害が原因でシロアリが発生した
シロアリ駆除に火災保険が適用されるのは、自然災害が原因でシロアリが発生したケースです。
台風でなくても、自然災害で家屋が歪んでしまった場合などに雨漏りが発生することもあるでしょう。
水漏れや雨漏りが発生したことで木材が湿気にやられ、シロアリ被害が出るケースもあります。
ただし、地震や地質が原因の土砂崩れなどで発生したものは火災保険の対象外となるので注意しましょう。
ケース③雪が原因でシロアリが発生した
シロアリ駆除に火災保険が適用されるケースとして、雪が原因でシロアリが発生した場合が挙げられます。
大量の雪が屋根に降り積もると、建物が圧迫されて屋根が破損してしまうこともあります。それによって水漏れが起きると、屋根の下地部分が湿気にやられ、シロアリが発生することもあるでしょう。
火災保険は積雪による被害も補償されるため、シロアリ駆除による被害も対象となる可能性があります。
シロアリ駆除で火災保険が適用される際の注意点
シロアリ駆除で火災保険が適用される際の注意点は、あくまでも自然災害によって引き起こされた場合のみ適用されることです。
シロアリの被害が自然災害に起因していると証明する証拠がないと適用されないので注意しましょう。

シロアリの駆除費用を抑えるなら雑損控除を活用しよう

シロアリの駆除費用を抑えるなら、雑損控除を活用するのもおすすめです。
- 確定申告で雑損控除を利用する条件
- 雑損控除の計算方法
- 雑損控除の申請方法
- 災害が原因なら軽減免除が利用できる
詳しく解説します。
確定申告で雑損控除を利用する条件
シロアリ駆除費用を抑えるために、確定申告で雑損控除を利用する条件は以下のとおりです。
雑損控除とは、災害や盗難、横領などで資産に損害を受けた際に、申請することで総所得金額から一定の所得控除を受けられるものです。
- 納税者、または納税者と生計をともにする配偶者や親族で、該当年度の総所得金額が38万円以下であること
- 損害を受けた資産は生活に欠かせないものであること
- 疎外の具体性が証明できること
雑損控除を利用するためには、上記の条件を満たしている必要があります。
雑損控除の計算方法
シロアリ駆除費用を抑えるために雑損控除を利用する場合、計算方法は以下の2通りがあります。
- ①差引損失額-5万円
- ②差引損失額-(総所得金額×10%)
上記の計算のうち、どちらか答えが大きいほうが適用されます。
雑損控除の申請方法
雑損控除の申請方法を詳しく解説します。
①シロアリ駆除業者から領収書をもらう
雑損控除の申請をするには、まずシロアリ駆除業者から領収書をもらいます。領収書を用意することで、実際にシロアリ駆除を行ったことの証明になります。
②必要書類を用意する
雑損控除の申請をするために、必要な書類を用意しましょう。必要となる書類は以下のとおりです。
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- シロアリ駆除または修繕費用の領収書
- マイナンバーカード
- 還付金を受け取るための銀行口座情報
確定申告の際に慌てないためにも、前もって準備をしておきましょう。
③確定申告書を作成する
雑損控除の申請をするために、確定申告書を作成します。必要事項を入力し、2月半ばから3月半ばの間に確定申告を行ってください。
④確定申告書を提出する
雑損控除の申請を受けるために、確定申告書を提出しましょう。領収書などの必要書類や源泉徴収所などを添付し、税務署に提出します。
⑤還付金を受け取る
最後に、雑損控除の還付金を受け取ります。指定の銀行口座に入金があるので、確認してください。


災害が原因なら軽減免除が利用できる
シロアリによる被害が災害に該当する場合、軽減免除が利用できます。その年の所得金額の合計が1000万円以下だった方が該当し、納税者の選択によって雑損控除とどちらか有効な方法を選べます。
シロアリ駆除で雑損控除を利用する際の注意点

シロアリ駆除で雑損控除を利用する際の注意点は以下の3つです。
- シロアリの予防は控除の対象外
- 事業用の建物や別荘は控除対象にならない
- 業者に依頼した費用でなければ対象にならない
一つずつ解説します。
注意点①シロアリの予防は控除の対象外
シロアリ駆除で雑損控除を利用する際の注意点は、シロアリの予防は控除の対象外となることです。
シロアリの予防は家を守るために大切なことですが、残念ながら雑損控除の対象とはなりません。
雑損控除は実際に発生した損失に対する救済が目的のため、予防処置は対象とならないのです。
注意点②事業用の建物や別荘は控除対象にならない
シロアリ駆除で雑損控除を利用する際の注意点として、事業用の建物や別荘は控除対象にならない点が挙げられます。
雑損控除を受ける条件の1つが、「損害を受けた資産が生活に欠かせないものである」というものです。
住んでいる家などが該当しますが、事業用の建物や別荘は対象外となります。

注意点③業者に依頼した費用でなければ対象にならない
シロアリ駆除で雑損控除を利用する際の注意点の3つ目は、業者に依頼した費用でなければ対象にならないことです。
自分で駆除を行った際の薬品代やDIY代などは対象外となるので注意しましょう。
補助金は出ないがシロアリ駆除が負担されるケース

補助金は出ないがシロアリ駆除が負担されるケースは以下の3つです。
- ケース①新築物件の場合
- ケース②中古物件の場合
- ケース③賃貸物件の場合
一つずつ解説します。
ケース①新築物件の場合
補助金は出ないがシロアリ駆除が負担されるケースとして、新築物件の場合が挙げられます。
新築物件は、住宅の品質確保の推進などに関する法律(品確法)に基づき、引渡しから10年間はシロアリ駆除の費用が負担される場合があります。
ただし、シロアリ被害の原因が「施工不良」であった場合に限るため、しっかりと証明できることが条件です。
ケース②中古物件の場合
補助金は出ないがシロアリ駆除が負担されるケースとして、中古物件の場合を見ていきましょう。
中古物件の場合、以下の条件で「契約不適合責任」が適用されます。
- 契約時にシロアリ被害がないと説明されていた(シロアリ被害に気付かなかった)
- 被害について告知されずに売買された
ただし、シロアリ被害を知ったときから1年以内に売主へ通知する必要があるので注意してください。


ケース③賃貸物件の場合
補助金は出ないがシロアリ駆除が負担されるケースの3つ目は、賃貸物件の場合です。賃貸物件でシロアリが発生した場合は、賃貸契約書に基づき、大家または管理会社に駆除費用の負担を依頼しましょう。
連絡せずにシロアリ駆除業者を勝手に手配してしまうと、思わぬトラブルを招く可能性もあります。
補助金が出ない場合にチェック!シロアリの駆除費用自体を安くする方法

補助金が出ない場合にチェックしたい、シロアリの駆除費用自体を安くする方法を解説します。
- ホームセンターや個人事業主に依頼する
- 複数の業者で相見積もりを取る
- 5年以上の保証制度がある業者に依頼する
詳しく見ていきましょう。
ホームセンターや個人事業主に依頼する
シロアリの駆除費用自体を安くする方法は、ホームセンターや個人事業主に依頼することです。
ホームセンターや個人事業主も、シロアリ駆除を行っている場合があります。一般的な業者よりも安く対応しているところもあるので、一度見積もりを出してみると良いでしょう。
複数の業者で相見積もりを取る
シロアリの駆除費用自体を安くする方法として、複数の業者で相見積もりを取ることが挙げられます。
シロアリの駆除費用は業者によって異なるため、1つの業者に見積もりを取っただけで決めてしまうのは危険です。
万が一相場とは異なる金額を提示されていても気づけないため、少なくとも2~3社に見積もりを取ることをおすすめします。

5年以上の保証制度がある業者に依頼する
シロアリの駆除費用自体を安くする方法の3つ目は、5年以上の保証制度がある業者に依頼することです。
一般的に、シロアリ駆除に使われる薬剤の有効期限は5年程度といわれています。保証期間が5年ほどあれば、次のシロアリ駆除を行うまでに被害が出た場合に、無償または低価格で対応してもらえます。
シロアリ駆除の資金が用意できない場合はどうする?

シロアリ駆除の資金が用意できない場合、工事を行う前に業者へ相談しましょう。シロアリ駆除費用には、床下湿気工事や補修工事など、必須ではない作業も含まれています。
行ったほうが安心の工事ではありますが、資金が用意できない場合は工事を省くことも検討してみてください。
シロアリ駆除に補助金は出ないが費用の安さを売りにする業者には注意

シロアリ駆除に補助金は出ませんが、費用の安さを売りにした業者には注意が必要です。費用の安さを売りにする業者には、以下のようなリスクがあります。
- 施工のクオリティが低い
- 追加費用を請求される
安くシロアリ駆除を行っても、施工技術が低く再発してしまっては意味がありません。また、見積もりでは提示されなかった追加費用を請求されることもあるため注意してください。


補助金対象外のシロアリ駆除におすすめな業者4選

補助金対象外のシロアリ駆除におすすめな業者を4つ紹介します。
シロアリ110番

シロアリ110番は、累計お問い合わせ件数500万件を突破した害虫駆除業者です。相談や見積もりは無料で、最短即日でシロアリの駆除に来てもらえます。
正式な見積もり後の追加料金は一切発生しないため、安心して利用できるのが特徴です。わかりやすい料金携帯なので、補助金が出ないシロアリ駆除でも安心の価格で施工してもらえます。
ムシプロテック

ムシプロテックは、「早い・安い・信頼」をコンセプトにした害虫駆除業者です。補助金の対象外であるシロアリ駆除も、業界トップクラスの最安値で施工してもらえます。
年間実績は1万件以上と、施工に関する知識や経験も豊富です。また、現地見積もりや出張費用、追加請求などは一切ありません。
シロアリ駆除のキャッツ

シロアリ駆除のキャッツは、最短即日で利用できる害虫駆除業者です。調査や見積もりは費用がかからず、補助金の出ないシロアリ駆除も業界最安級の価格で施工してもらえます。
また、無料の定期点検を年に1回実施し、アフターサービスとして5年保証がついているなど、安心のポイントも充実しています。
サンキョークリーンサービス

出典:sankyo64.com
サンキョークリーンサービスは、経験と実績が豊富な害虫駆除業者です。シロアリの駆除や予防の実績も豊富で、シロアリ防除士が在籍しています。
補助金対象外のシロアリ駆除も、調査や見積もりなど余分な費用が発生せず、リーズナブルな価格で施工してもらえます。
施工後1年目、3年目、5年目に無料の定期点検を実施してもらえるのもポイントです。